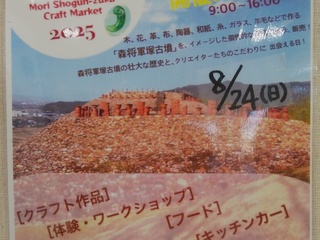

本日開催のクラフト展に出展されている、コリカンチャ工房さんが、午前・午後と2回演奏して下さいました。
コリカンチャ工房さんは、様々なアンデス民族楽器の「製作者であり、演奏者であり、研究者です。」と館長さんから紹介があり、自作の【アルパアンディーナ】というハープのような楽器を使って演奏されました。
ハープのように座って演奏するのではなく立って、34本の弦の30㎏くらいの重さの大型の楽器を抱くように演奏されていました。
楽器にあしらわれている模様にも意味があり、楽器の下の穴は太陽を、上が星、下がハチドリ、左右が三日月を表しているそうです。
表面の装飾は、楽器のひび割れをつなぎ合わせるためで、修理しながら大切に使われていました。



歌いながら劇をする、悲恋の曲【ヤラビ】(間違っていたらスミマセン)を演奏され、素朴で哀愁のある音色に、1600年前の森将軍塚が築造された頃にも、当時の人々は歌をうたったり、楽器を演奏していたのだろうかと思いを馳せました。
次に、【ケーナチョ】というケーナより長い、尺八と同じくらいの長さの楽器で、有名な【コンドルは飛んでいく】を演奏して下さいました。不思議な音色ながら力強さもある楽器でした。
【コンドルは飛んでいく】は、ペルーでも親しまれている、第2の国歌のような曲だそうです。コンドルは翼を広げると4m、頭から爪先まで1.5mもある巨大な鳥で、そんな大きな鳥が、雄大に飛べる遮るものがない環境が、いまだにペルーにはあるのかと、コンドルが飛んでいる姿を思い浮かべながら、ロマンを感じ感慨にふけりました。
また、シルクロードを伝わって日本に伝来した【正倉院尺八】は、ケーナに似ているそうです。
演奏の合間にも、様々なお話しをしてくださり、アンデスで楽器を習うのに、文字無し・楽譜無しのため、聞いて覚えたという苦労話や、アンデスは、石を使った巨石文化で、インカの首都クスコ(標高3400m)から80㎞離れたアヤクーチョという(テロが多い)街には、6枚の岩を並べた遺跡があり、ペルーでは森将軍塚古墳にそっくりな遺跡をよく見掛けるそうで、森将軍塚に親近感をもたれている様子でした。
質問の時間帯にも、熱心に質問される方々に気さくに応じられ、貴重な楽器にも触らせて頂けました。
古墳時代の日本とインカ帝国時代のアンデス(ペルー)においては、人々と自然との距離が近く、自然に畏敬の念を抱いて、日々の営みや社会を構築していたことが共通しているのでは?と感じました。
最後に、【コリカンチャ】とはどういう意味か?質問し忘れていまいました。
機会があれば尋ねたいです。
次回のクラフト展は、9/15(月・祝)9:00-16:00 科野の里歴史公園内の芝生広場
小雨決行・荒天中止
同時開催 KOM古墳deオープンマイク
コリカンチャ工房さんも出展します!
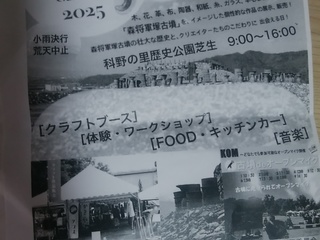
| コミュニティ名 | 森将軍塚古墳友の会 |
|---|---|
| コミュニティの種類 | 市民活動団体 |
| ジャンル | 文化・伝統 / まちづくり・地域活性化 / 観光・レジャー |
| キーワード | 長期 / 社会人 / 大学生・専門学生PO / シニア / ボランティア / 初心者歓迎 / イベント |
| 活動エリア | 長野県千曲市 |
| 主な活動場所 | 森将軍塚古墳 |
| 主な活動日・時間 | 不定期 |
| 活動費 |
無料 |